

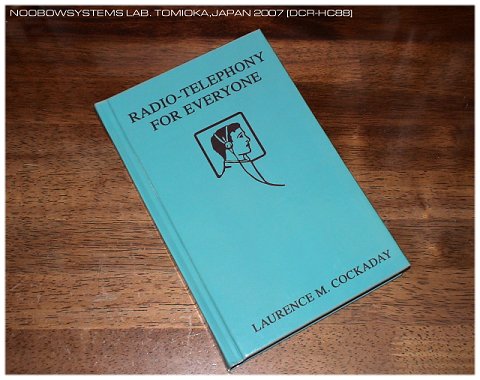
|
Radio Telephony for Everyone Laurence M. Cockaday Merchant Books ISBN: 1-933998-07-5 ¥4,197 |
|
AM音声変調の技術が実用化されし、一般大衆向けのラジオ放送が始まって家庭にラジオ受信機が入り始めると、
一般ユーザのなかにも調子の悪い機械をなんとかしようといろいろ勉強し始める人が現れます。
この本はそんなラジオサービシング入門者のために書かれた無線電話技術のテキストで、
エレクトロニクスの基礎、無線電話の仕組みと回路動作、
無線送受信機の製作方法とトラブルシューティングおよびメインテナンスについて書かれています。 この本は明らかにリプリントなのですが、 リプリントに際してのプリフェイスが一切ありません。 オリジナル本の扉にも何年の出版なのか書かれておらず(あるいは消されている?)、 最初のページ-リプリントの扉の前-には、はっきりと"Copyright (C) 2006 Merchant Books"と書かれています。 およよ? こういったリプリント本にはたいてい、内容には現在では誤っていると判明していることや、 現在では危険と考えられているまたは禁止されていることが書かれているので注意するように・・・ との警告文が掲載されていたりしますが、そういったものも一切ありません。 出版元を調べてみると、どうやらこの会社はもともと装丁と製本を主とする会社で、 古い技術書のリプリントも多く出しています。 技術書のリプリントなら勝手に復刻して売っても文句言われることは少なかろう・・・との判断なのかもしれません。 日本にももちろん、失われつつある良書が数多くあり、少ない現存品はオークション等で高価で取引されています。 先人の技術と知識を後世に伝えるためにも、この手のリプリントは(法的な問題を含みながらも)もっと普及していいのではと思いました。 |
|
さて、この本は読みながらいつごろのものなのかを推測することにしましょう。
ハードカバー製本で、213ページ。
イラストや写真も多く掲載されています。
リプリントの品質も良好。
著者のLaurence M. CockadayはPopular Radio誌に記事を掲載していた人で、
再生回路の選択度と安定性を高める工夫として発表されたスタビライザーコイルをもつ"4回路チューナ"は、
別名"Cockaday Circuit"として知られています。 Chapter 1 Electrical Theory upon which Radio is founded 電気物理の基礎をわかりやすく説明しています。 ただしオームの法則には触れられておらず、 静電容量はコンデンサという語のみが使われており、 キャパシタとかキャパシティという語は現れていません。 インダクタンスという語は使われていてその記号はLですが、 なぜインダクタンスがLなのかは説明がありません。 初心者向けに噛み砕いて説明しているのでしょうが、 それにしてもちょっと不正確な記述が気になります。 Chapter 2 General Theory of Radio Waves 電波とはなにか、を説明しています。 音波とのアナロジーを使っていますが、 「音叉をもっと高速に振動させればやがて音叉が温かくなってくる、 さらに振動数を増せば金属が赤く光りだして光が放射されてくる・・・ だから音も熱も光も同じ振動で、ただ違うのは振動数だけだ」 となると、ズブの素人向けの啓蒙書としても不正確に過ぎないかなあ? この本では「電波はイーサの振動」という概念は出てきません。 電波は振動数10,000サイクル毎秒から3,000,000サイクル毎秒の振動だ、 とされており、3MHz以上の高い周波数は全く未知であったようです。 波長帯と電波の使用区分が書かれていますが、当然この時代アマチュア無線の波長は200メートル以下になっており、 それ以外の用途は書かれていません。 Chapter 3 The Vacuum Tube, for Generating Oscillations オーディオンとかエレクトロン・リレーという語も残っていますが、 Vacuum Tubeという言葉が一般名詞として使われています。 3極真空管の動作原理が書かれていますが、 まだ古典管の時代。 傍熱型真空管は登場しておらず、 オーディオン(3極真空管)がAM変調された信号を復調する動作の説明は不正確です。 このチャプターではいかにして真空管が高周波信号を発生させるか、 について書かれており、それ以前に使用されていたスパーク・ギャップについては書かれていません。 送信機が機械式から電子式に変わっていく時代でした。 Chapter 4 Modulation 吸収変調や電磁変調などいくつかの原始的なAM変調の方法が説明された後、 「他の方式にくらべて明らかに秀でている方法」として ハイシング氏 の発明による定電流変調が取り上げられています。 Chapter 5 The Aerial or Antenna ワイヤーアンテナは静電方式アンテナ、ループアンテナは電磁方式アンテナと紹介されています。 静電方式アンテナは大地との間にコンデンサを形成することにより動作すると考えられており、 アンテナの最適な全長は使おうとする波長と関係があるとは書かれていません。 当然、インピーダンスとかローディングとかについても記述はなし。 さらに、L型ワイヤーアンテナの指向性についての記述はあきらかに誤っています。 Chapter 6 Tuning Apparatus for Receiving 同調回路の原理を紹介しています。 いわゆる並列同調回路も紹介されていますが、全体としてまだまだ発展途上で、 バリオカップラとバリオメータだけで構成された、キャパシタのないチューニング回路も残っています。 Chapter 7 The Crystal Detector and the Vacuum Tube すでに廃れたデバイスとしてコヒーラに触れた後、鉱石検波器の説明。 使われているのはカーボランダム検波器、シリコン検波器、そしてガレナ(方鉛鉱)検波器。 シリコン検波器は動作させるためには電池ですこしばかり直流電圧をかけてやる必要があるがカーボランダムよりは感度がよい、 ガレナは最良点の探りが難しいが、いったん最良点が見つかればカーボランダムやシリコンよりも感度がよい・・・と書かれています。 その後、3極真空管による、グリッドリークをもつ検波回路が紹介されています。 Chapter 8 Regeneration and Amplification アームストロングによる再生回路とそのバリエーションが詳細に紹介されています。 高感度かつ安定な動作を求めていますが、スクリーングリッド電圧制御が可能な傍熱型5極管はまだ開発されておらず、 バリオメータなど複雑で高価なデバイスを用い、調整に苦心している様子がわかります。 1921年10月のPaul Formamn Godley氏 (*1) による大西洋横断受信実験と、 そのとき使われた回路も紹介されています。 しめくくりに、高周波2段増幅・再生検波・低周波2段増幅式で室内型ループアンテナを用いラッパ型ラウドスピーカを駆動する形式が 「現在入手しうる最も高性能なラジオ受信機」として紹介されています。 「この先ラジオが大半の家庭に普及するとしたらこの形態になるだろう・・・ 100世帯が入っている都会のアパートの窓という窓から100本の100フィートのワイヤーアンテナが伸びることは大家さんが許さないだろうから。」
*1: アームストロング氏の再生回路を2つのバリオメータを使って短波帯用に改良しアマチュアに紹介した、「アマチュア無線用受信機の生みの親」
Chapter 9 Specifications and Instructions for Building a Radio Telephone Transmitter 自分でつくった機械で電波を出すということだけでさえエキサイティングなのに、 自分の声を送れるとなればこれはすごいことです。 この時代、いよいよ16歳の子供が自分の家で無線電話送信機を作れるように (高価な真空管を買うことができたならば) なりました。 このチャプターでは、自分でつくってみたい人のために、2球式のAMトランスミッタの製作方法を紹介しています。 使うのは型番は書かれていませんが5Wクラスの送信用真空管2本。 真ん丸くて先端が尖った形をした、いまでいう古典管を使っています。 1本を発振管、もう1本を変調管として使い、変調方式は定電流変調。 定電流変調は特に日本ではハイシング変調と呼ばれている方式です。 変調トランスを使わずに実現できるので アマチュアの自作には適した方式でしたが、 周波数の変動や非直線性のためにスプラッタを発生させてしまいがちで、 安定して深い変調を得ることは困難でした。 この時代の空は、おそらくひどい音質とスプラッタだらけの、 しかしチャレンジングなアマチュアの声が飛び交っていたのでしょう。 定電流変調は I.C.S. Radio Operators Handbook (1923) にも取り上げられています。 回路には高価なバリコンは使用しておらず、 同調はコイルタップ切り替え式で波長350メートルから200メートルまでをカバー。 あれっ? この時代 すでにアマチュアは200メートルより上に行っちゃいけないんじゃなかったっけ? Chapter 10 Specifications and Instructions for Building a Radio Receiver 受信回路が3種類取り上げられています。 最初は、自作のスライド式L可変コイルによる、鉱石検波ラジオ。 並列同調用のキャパシタすらなく、しかも感度の低いテレホン(受話器)を使っているのですから、 その性能や推して知るべし。 二つ目はアンテナコイルにルースカプラを使い、真空管検波回路を使ったもの。 これでも同調はL可変のみで、並列キャパシタは存在せず。 3つめはバリオメータを2つ使った再生検波プラス低周波2段増幅の3球式。 Chapter 11 Care and Maintenance of Apparatus 著者は「この章が一番大切だ」と前置きして、ラジオの調整・維持・修理の心構えや実践の方法を書いています。 著者の家に知人が尋ねてきているときにラジオの調子が悪くなり、 自分の腕前を見せてやろうと知人の前で修理に取り掛かった・・・というくだりは、 技術解説書というよりはエッセイの風情で、その顛末を楽しめます。 トラブルシューティングといってもデバイスの数は少なく、シグナル トレーシングという技法を説明するまでもなく、 さらに一般ユーザはテスタもなにも機材といえるようなものは保有しておらず、 となると、なかなか困難。 強調しているのは、トラブルの大半は設備の故障ではなくて、正しい調整方法を知らないユーザの責によるものだということ。 だから正しい使用方法を理解し、それを伝えるのが重要、と書かれています。 80年経った今、これはちょうどPCのトラブルシューティングに似ているかも。 |
|
Chapter 11に出てくる放送局のコールサインから、また大西洋横断受信実験について書かれていることから、
1922年以降の著作だと思われます。
また、巻末の「ラジオ用語集」を含めた全編にスーパーヘテロダインという語はまったく出てきていません。
1924年になるとRadiola Superheterodyneが登場します。
これ以降であれば用語集に必ず入ってくるだろうから、
本書の内容は1923年までのもののはず。
ということで、私の推測は1922年春から1923年秋ころまでの1年半の間に発行されたものでしょう。
|